少年事件「抗告」の着眼点

このページをご覧の方の中には、
- 少年審判で少年院送致となった
- 少年審判で思っていたよりも重い結果となった
という方がいらっしゃるかもしれません。
「抗告」という言葉をご存じでしょうか?
「抗告」とは、家庭裁判所の審判の結果、保護処分決定がなされた場合に、不服申立てを行うことを言います。刑事裁判における控訴に相当するものです。
このページでは、審判の結果に対して不服申立てを行う「抗告」について説明します。
抗告3つのポイント
- 抗告は短い期間の中で申立てる必要がある
- 執行停止がない
- 処分が変更される確率は低い
申立ての期間
家庭裁判所の審判において、保護観察処分、児童自立支援施設・児童養護施設送致処分、少年院送致処分が出された場合に、抗告申立を行うことができます。そして、抗告を申立てすることができるのは、少年、法定代理人、付添人です。
そして、抗告申出の期間は、決定の告知のあった日の翌日から起算して2週間です(少年法32条)。申立書の提出先は原裁判所となります。
執行停止がない
成人の事件であれば、実刑判決に対し控訴をすると刑務所への収容が一旦ストップとなります。
しかし、少年事件の場合には、少年院送致の執行が停止されないのがポイントです。
抗告の申立てによって原審保護処分の執行停止の効力が認められず、施設収容の保護処分の場合には決定から間もなく、少年は少年院等に送致されます。つまり、抗告をしても一旦、少年院に入所することとなります。
弁護士が裁判所に対して執行停止の申立てを行うことができますが、あくまで裁判所の職権の発動を促すにとどまります。
処分が変更される確率は低い
抗告審は書面審理であり、ほとんどの場合で審判が開かれず、抗告により処分が変更される確率はきわめて低いです。そのため、抗告をされるのであれば、変更の可能性を少しでも上げるため、弁護士を通じて行われるのが通常です。
抗告をするための3つの理由
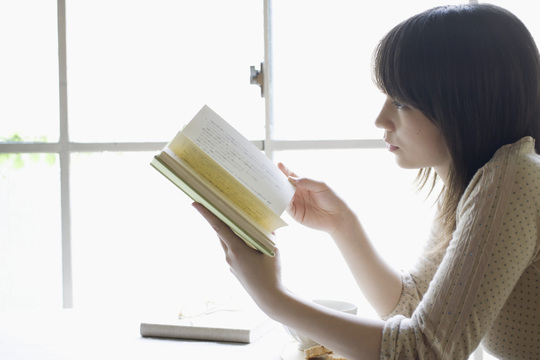
決定に影響を及ぼす法令違反
法令違反には、手続きに関する法令違反と実体法に関する法令違反とが含まれます。具体例としては、審判に際して保護者の呼び出しを欠いた場合などが挙げられます。
重大な事実誤認
証拠となる資料により認定されるべき事実と原決定が認定した事実が食い違うことを言います。
また「重大」とは、決定の主文に影響を及ぼす事実認定の誤りをさします。
処分の著しい不当
保護処分決定が具体的事案に即して適切妥当な処遇でないことをさします。
具体的には
- 要保護性がないあるいは要保護性が低く保護処分に付する必要がないのに保護処分に付した場合
- 保護処分の種類の選択を誤った場合
- 少年院送致決定の場合に少年院の種類の選択を誤った場合
をさします。
※処分の著しい不当の判断要素として、前回の審判後の少年の内省の進み方や被害回復・示談の成立なども考慮されます。
※処分の著しい不当のみを理由とする抗告の申立ての場合、申立てから1か月前後で抗告棄却決定がなされることが少なからずあります。
再抗告について

高等裁判所による抗告審の決定に対して不服がある場合、最高裁判所にさらに抗告することができ、「再抗告」といいます。
再抗告理由は
- 憲法に違反し、もしくは憲法の解釈に誤りがあること
- 最高裁判所、もしくは控訴裁判所である高等裁判所の判例と相反する判断をしたこと
です。
再抗告ができるのは、少年、少年の法定代理人、付添人(弁護士)です。また、再抗告をする際には、再抗告理由を記載した最高裁判所宛の再抗告申立書を作成し、抗告裁判所に提出する必要があります。
弁護士のサポートとは?

弁護士のサポートとしては、
- 抗告理由の検討
- 記録の閲覧等による抗告の準備
- 抗告申立書の作成・提出
等があります。
藤井寺法律事務所の特徴

当事務所の弁護士は、これまで大阪だけでなく多くの地域から少年事件のご依頼をいただいております。
少年事件・少年犯罪の初回の無料相談を行っております。そのため、まずは費用を気にせず、今後手続きの流れや見通しをはじめ、各種対応について聴くことができます。
身体を拘束されているお子様の下へ最短即日に接見に向かう接見サービスもご提供しております。
